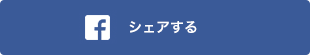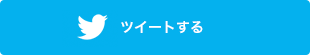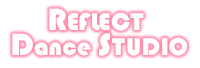201509/28
ベースの音作りで注意すべきポイント
前回はベースの音作り手順について書かせて頂きましたが、今回はその音作りで注意しておきたいポイントについて書いていきたいと思います。
ベースの音作りで注意すべきポイント

ケーブルの抜き差しはできるだけ電源を入れる前に済ませておき、やむを得ず抜き差しする場合はボリュームを0にして完全に音が出ないようにしてからが基本となります。
シールドは接触不良を起こしてトラブルを招きやすいので、アンプに接続する前にプラグをクロスなどで乾拭きしておく習慣をつけておくといいです。
また、ベースアンプの消費電力はとても大きいので、なるべく電源タップを使ったたこ足配線は避けて、余裕のある電源を確保するよう心がけましょう。
参考:ベースアンプの機材紹介 AMPEG編
ベースとベースアンプの間には無駄な機材が接続されていない方が確実に音質のロスは少なくなります。
ベースアンプの機能は試してみて、使わないようであればできるだけバイパスさせましょう。
エフェクターなどを使う場合も、まずはベースとアンプを直結にして音作りすることをおすすめします。
エフェクターをバイパスにしていてもシールドの全長が長くなるなど、音は少なからず変化するので、これを認識したうえでエフェクターを使った方が、音作りがスムーズになるためです。
基本的な音作りはバンド練習を始める前に素早く終わらせておきたいところですが、バンドで演奏場合はベースだけで音色を成立させてもあまり意味がなく、あくまでアンサンブルの中で鳴っているベースの音を想定して音作りをするのが重要です。
例えば、中低域はボーカルがよく聴こえる様に空けておくなど、バンドの特性に合わせてベースの音色を作っていきましょう。

前回の音作り手順の記事でも書いていましたが、トーンコントロールはざっくりと機能別にとらえると音作りが簡単になると思います。
TREBLEもBASSも、必要十分な量を見極めることが重要で、演奏する音楽性によってある程度の幅はあるものの、ベーシストにはあまり選択の自由がないかもしれませんが、逆にMIDDLEはベーシストの好みで設定でき、個性が反映されるほど重要な要素と言えるでしょう。
それだけにMIDDLEは入念に設定したいところですが、だからこそMIDDLEがひとつしかない潔い機種では上げ下げできる音域によって好みがハッキリと分かれるものですね。
トーンコントロールには操作できる帯域の周波数が書いてある機種も多いですが、周波数の数字のイメージと実際の音域のイメージをある程度リンクさせておくと、音作りをする上で何かと便利です。
グライコがある場合はベースを弾きながら各バンドを上げ下げすることで、その周波数の音色のイメージがつかめるでしょう。
ただし、機種によってはある帯域を操作することで別の帯域に影響を与えてしまうことがあったり、単に表記された周波数と実際の周波数がずれていたりするので、あくまで表記された数字を鵜呑みにせず、耳で判断して音作りをするようにしましょう。
とはいえ、なかなか耳だけで判断するのは難しいですよね。
日々練習を重ねていくと耳も肥えてくると思いますので、きっとこだわりの音が見つかるはずです!

リフレクトスタジオでは、各部屋ベースヘッドアンプを2台常設しており、アンペグ、ハートキー、お好きな方をお選びいただけますので、今回のポイントを踏まえてぜひ練習にいらしてください。
今回はここまでにしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連するおすすめ記事
オススメのスタジオ
 今池店
今池店-
A3スタジオ【今池店】〜6名くらい
Astタイプは14帖~15帖という余裕の広さを確保しながら他では考えられないリーズナブルな価格!専門家が計算した反響調整により、迫力のある音を残しつつ、全ての音がはっきり聞こえるようにつくられています。一...
 新栄店
新栄店-
C2スタジオ【新栄店】〜10名くらい
22帖の驚異的な広さ!!ビッグバンドでも余裕で演奏できる環境です!! 導入スタジオ唯一!??ドラムセットにSAKAEから最高最上機種CELESTIALを採用!!! 1000w級スピーカー+フットモニタで抜群のモニタリング! ライン録...
 新栄店
新栄店-
A1スタジオ【新栄店】〜6名くらい
Astタイプは専門家が集音計算を実施し、デッドに吸音を整えつつ、迫力も出るようにほどよく反響音もわざと残した抜群の音周り設計! 3つの転がしモニタとドラム専用のモニタの計4つのスピーカーを常設最適なモニタ...
 新栄店
新栄店-
B1スタジオ【新栄店】〜7名くらい
16帖の広さを確保!最も多くの吸音材を使用した部屋で、極限までデッドな環境に! Bstはスタンドタイプのスピーカーを設置!スッキリしたキレイな音周りを表現! ドラムはTAMA最高グレードSTARCLASSIC採用!!全ての...