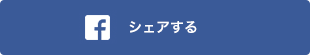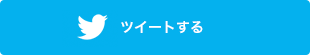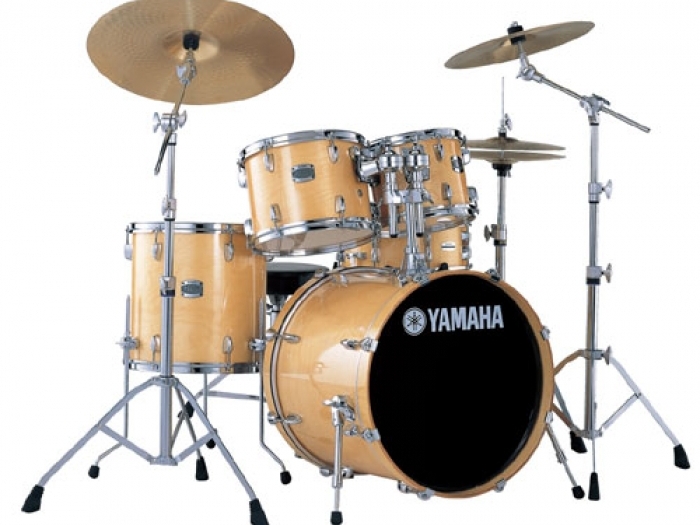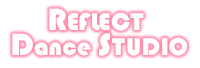1

202507/16
歌の音程とピッチの違いとは?正しい理解と練習法

歌を歌っていると、「音程がずれているよ」「ピッチが安定していないね」といった言葉を耳にしたことはありませんか?
一見すると似たような表現ですが、「音程」と「ピッチ」はそれぞれ異なる意味を持つ音楽用語であり、正しく理解することが歌唱力の向上には欠かせません。
この二つの言葉の違いが曖昧なままでは、自分のどこをどう直せばよいのか分からず、練習の方向性も定まりにくくなってしまいます。
たとえば、「音程が悪い」と言われても、それがメロディーの流れに問題があるのか、単に一音ごとの高さがズレているだけなのかを正確に判断できなければ、的確な改善策を取るのは難しいものです。
本記事では、「音程」と「ピッチ」の違いを丁寧に解説し、それぞれをどう捉え、どのようにトレーニングすればよいかをわかりやすくご紹介します。
また、ピッチ補正ツールの活用方法や、ボイストレーニングの活かし方についても詳しく解説しています。
初心者の方はもちろん、今まで何となく自己流で歌ってきた方にとっても、歌の技術を見直す良い機会になるはずです。
まずは、「音程」と「ピッチ」の違いをしっかりと理解していきましょう!
音程とピッチの基礎知識

歌を正しく、美しく歌うためには、音程とピッチという2つの要素を正しく理解しておくことが非常に重要です。
この2つは、どちらも「音の高さ」に関係する概念ですが、それぞれに注目しているポイントが異なります。
それぞれの意味と違いを、できるだけ分かりやすく解説していきます!
音程とは?2つの音の間隔を理解しよう

音程とは、簡単にいえば「2つの音の間隔」や「音の距離感」のことです。
たとえば「ド」と「ミ」のように、異なる高さの音が連なったとき、その間にどれくらいの距離があるかを表すのが音程です。
音楽の世界では、音程を「2度」「3度」「5度」などと数値で表します。
これらは、音階上での位置関係に基づいており、例えば「ド」から「ミ」は3つ目の音なので「長3度」となります。
この距離感を正確に表現できるかどうかが、メロディを正しく歌えるかに直結します。
たとえば、ある曲のメロディが「ド→ミ→ソ→ミ→ド」という音の流れだったとしましょう。
このとき、「ド」から「ミ」へのジャンプ、「ミ」から「ソ」への跳躍など、それぞれの音と音の距離をきちんと把握して、適切な高さで歌うことが求められます。
この感覚が狂ってしまうと、正しく歌えているつもりでも「なんか違う」と感じられてしまうのです。
音程は、単なる“音の高さ”ではなく、“音と音の関係性”を理解し、それを正確に表現できる力です。
たとえば、和音を美しくハモらせたい場合にも、この音程の感覚は非常に重要です。
つまり、音程が良いとは、正確な音の距離を理解し、再現する力があるということなのです。
また、音程の感覚は「相対音感」と深く関係しています。
相対音感とは、基準の音を聞いたうえで、そこからの距離を感じ取る力です。
この能力が高い人は、楽器のキーが変わっても、歌のメロディラインを正しく再現できる傾向があります。
相対音感は後天的に身につけることができるため、日々の練習で十分に伸ばせる要素です。
ピッチとは?1音の高さに注目しよう

一方でピッチとは、「1つの音そのものの高さ」に焦点を当てた言葉です。
英語の"pitch"(音高)は、音の周波数(Hz)で表すこともあります。
たとえば、国際標準音として知られる「A4(ラの音)」は440Hzという周波数で振動しています。
ピッチが正しいとは、この基準値にぴったり合っているという意味なのです。
ピッチがずれている状態とは、本来出すべき音に対して少し高かったり、低かったりする状態を指します。
たとえば、カラオケで「この音は『ド』のはずなのに、微妙に高い『ド#』っぽくなってる」といったケースがまさにピッチのズレです。
ピッチの安定は、聞き手に安心感を与える要素です。
どんなに声質が良くても、ピッチが不安定だと「不安定に聞こえる」「不快に感じる」といった印象を与えてしまうことがあります。
特にバラードなどでロングトーンを使う際は、ピッチの精度が如実に表れます。
また、ピッチの感覚は「絶対音感」と関係があります。絶対音感とは、ある音を聞いた瞬間に「これはド」「これはファ」などと判断できる能力のことですが、これがなくてもピッチ感は十分に鍛えることができます。
多くのプロ歌手は、日常的にチューナーを使って自分のピッチをチェックしたり、録音した音声を聴いて修正点を見つけたりしています。つまり、ピッチの改善は「耳を鍛える」作業でもあるのです。
このように、音程とピッチはそれぞれ異なる視点から「音の高さ」に関わる概念です。それぞれの違いを理解することで、あなたの歌声の改善点がより明確になります。
音程とピッチの違いを掘り下げる

ここまで、音程とピッチという2つの用語について、それぞれの定義や意味を解説しました。
ここからは、その違いをより深く掘り下げ、「歌唱の中でどう違いが表れるのか」「なぜ混同されやすいのか」など、具体的な場面にそって解説していきます。
特に「音程が悪い」「ピッチがずれている」といった言葉の使われ方には微妙なニュアンスの差があり、これを正しく理解することで、練習の方向性も大きく変わってきます。
「音程が悪い」と「ピッチがずれてる」の違い

まず、「音程が悪い」と言われた場合と「ピッチがずれてる」と言われた場合では、指摘されている内容の焦点が異なります。
「音程が悪い」と言われたときは、音と音のつながり=メロディの流れに問題があるということを意味していることが多いです。
たとえば、ある曲で「ド→ミ→ソ→ファ」と歌うべきところを「ド→レ#→ソ→ミ」と歌ってしまっている場合、音のつながりそのものが違っており、これが“音程が悪い”とされる状態です。
つまり、正しい音の“幅”を掴めていないために、メロディ全体のラインが崩れてしまっているのです。
一方、「ピッチがずれている」という指摘は、今まさに出しているその1音の高さが、わずかに高かったり低かったりしていることを意味します。
音程の方向は合っていても、その音が「正確にチューニングされていない」状態といえます。
特に、ロングトーンや高音での声の安定性を問われる場面では、ピッチの精度が非常に重視されます。
たとえば、あなたがカラオケで「90点」以上を目指しているとします。
このとき、音程バーを外してしまうのは“音程のズレ”、バーに合っているのに「なんとなく不安定」と感じるのは“ピッチのズレ”の影響です。
このように、似ているようで意味は異なり、音程は「間隔」、ピッチは「高さそのもの」と押さえておくと理解しやすくなるのではないでしょうか。
この違いを理解することで、「どこを直せば歌が安定するのか」「どの練習を優先すべきか」が見えてくると思います。
単純に“音が外れる”と感じるだけで終わらせず、「音程のズレか?ピッチのブレか?」と冷静に分析できることが、上達の第一歩となるのです!
音感の違いが影響する認識のズレ

音程とピッチの違いを正しく理解するためには、人によって異なる“音感の発達度”についても知っておく必要があります。
音感には大きく分けて「絶対音感」と「相対音感」の2種類がありますが、どちらが強いかによって、音の感じ方や認識に差が出てきます。
たとえば、絶対音感を持っている人は、単音を聞いてそれが「ド」なのか「ファ」なのかを瞬時に判断できます。
そのため、ピッチのズレに非常に敏感です。
0.1音でも高かったり低かったりすると「なんかおかしい」と感じてしまうことがあります。
一方で、相対音感が発達している人は、音と音の関係性(=音程)を重視して音を捉えるため、多少ピッチがズレていても「全体のメロディが合っていればOK」と感じることがあります。
これが、音程は合っているけれど「なんとなく不安定」と聞こえる原因にもなります。
さらに、音感の強弱によって「ズレている」と感じるレベルにも個人差があり、自分ではうまく歌えているつもりでも、他人から見ると「ピッチがブレている」と思われることがあります。
これは、自分の耳と他人の耳の“ズレ”でもあり、歌唱においては特に注意すべきポイントです。
ピッチの精度を高めるには

「歌っているときに、なんとなく音が不安定に聞こえる」と感じたことはありませんか?
それは、ピッチのブレが原因かもしれません。
ピッチとは、1音1音の高さを正確に出すことを指します。
音程の正しさとは異なり、ピッチは音の高さそのものの精度が問われるため、わずかなズレが全体の印象に大きな影響を与えます。
ピッチの精度を高めるには、単に「耳で覚える」だけでは不十分です。客観的なツールと正しい練習法を組み合わせることで、初めて自分のピッチの癖を知り、修正していくことが可能になります。
それでは次に、チューナーを使った矯正法と、録音&フィードバックによる耳の鍛え方について解説していきます。
チューナーを使ったピッチ矯正練習法

チューナーとは、本来は楽器の調律に使われる機材ですが、近年はボーカルトレーニングにも広く活用されています。
特にスマホアプリでも高性能なチューナーが無料・低価格で使えるようになり、誰でも簡単にピッチの練習ができる環境が整っています。
チューナーを使った練習では、自分が発した音が「正確な音の高さ」からどれくらいズレているのかをリアルタイムで可視化することができます。
画面上にメーターやグラフで表示されるため、感覚ではなく数値と視覚で自分の音を確認できるのが最大のメリットです。
たとえば、「ド」の音を出す練習をする場合、チューナーが「♯気味」や「♭気味」と判定すれば、それを意識して修正していくことができます。
この練習を繰り返すことで、「自分の耳では合っていると思っていたけど、実際にはズレていた」という事実に気づくことができるようになり、音の高さを“正確に出す感覚”が育っていきます。
おすすめの方法は、毎日のウォームアップにチューナーを取り入れることです。
簡単なスケール練習や母音の発声(アー・イー・ウー・エー・オー)など、基礎的な発声練習の中で自分のピッチを確認するだけでも、大きな成果につながります。
録音とフィードバックで耳を鍛える

ピッチのズレを修正するうえで、もう一つ重要なのが「客観的に自分の声を聴く」ことです。
人間は歌っている最中、体内から響く骨伝導の影響で、実際の声の音高や質感を正確に把握できていないことがよくあります。
そこで有効なのが、自分の声を録音し、それを何度も聴き返すことです。
録音はスマホのボイスメモ機能やDAW(デジタル音楽制作ソフト)を使えば、手軽に始められます。
録音した音源を聴いてみると、「この部分だけ高くなっている」「語尾で音が落ちてしまっている」など、歌っているときには気づかなかったピッチの不安定さが浮き彫りになります。
また、伴奏やオケと一緒に録音することで、自分の声が曲の中でどう響いているかをより明確に把握できます。
音程を正確に取る練習方法

音程を正しく取る力は、ボーカル力を大きく左右する重要なスキルです。
ピッチが正しくても、出すべき音の位置を正確に理解していなければ、歌全体の印象は不安定に聞こえてしまいます。
音程とは「2つの音の間隔」であるため、常に「前の音」と「次の音」を関連づけて捉える力が求められます。
この音程感を鍛えるには、日々のトレーニングが欠かせません。
特に効果的なのが「スケール練習」や「楽譜を読む力の強化」、そして「相対音感の育成」です。
それでは、それぞれの練習法と、その効果的な活用方法について詳しくご紹介していきます。
スケール練習と音階意識の習慣化
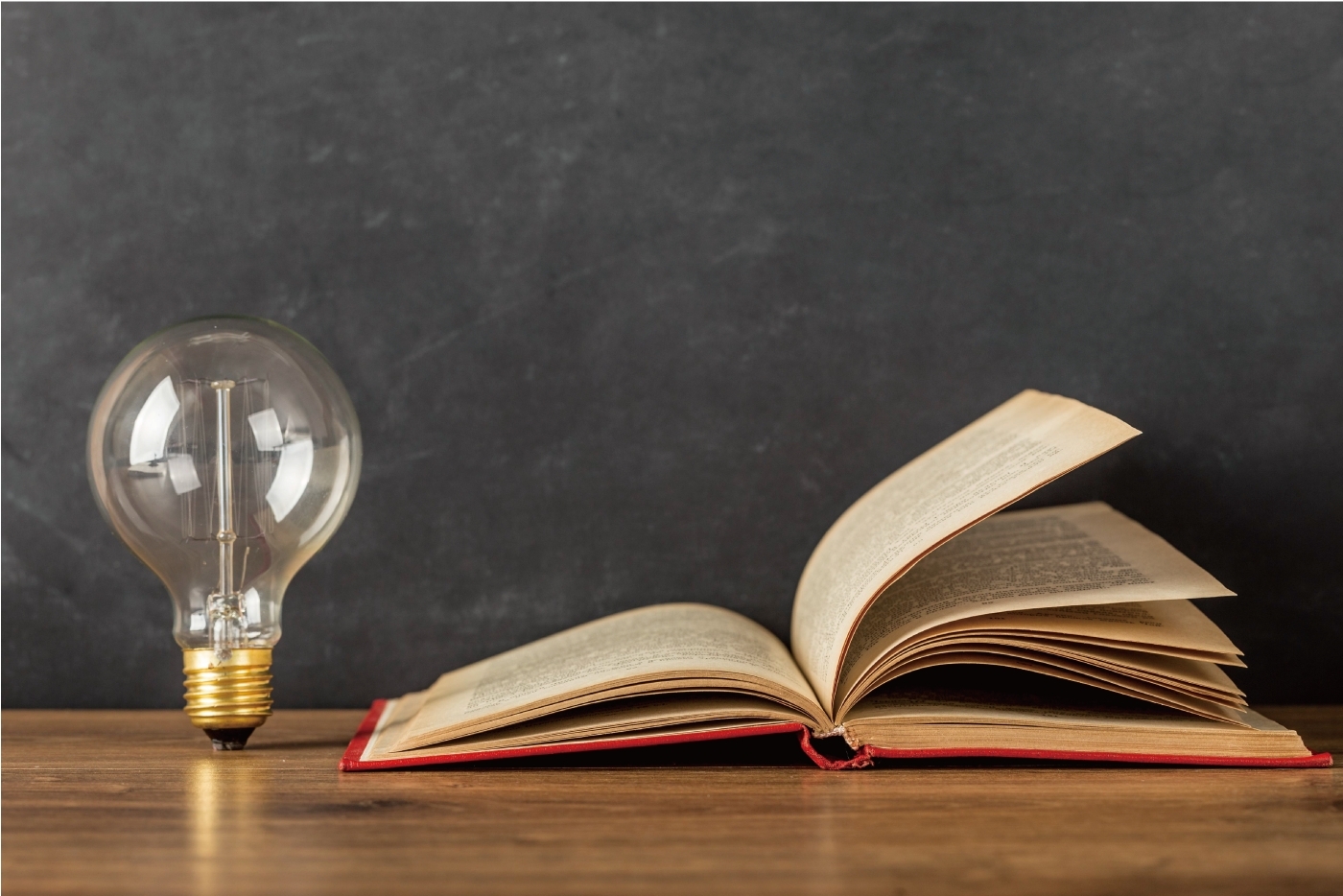
スケール練習(音階練習)は、音程感覚を鍛えるための最も基本かつ効果的な方法です。
たとえば、ドレミファソラシドといったメジャースケールを階段のように一音ずつ上がったり下がったりすることで、音と音の距離感=音程の感覚が身についていきます。
特に有効なのが、ピアノやキーボードを使いながら行う練習です。
自分が出す声と楽器の音を比べることで、「この音は高すぎた」「この音とこの音の間隔はもう少し広い」など、音の幅を身体で覚えることができます。
日々のルーティンとして、以下のようなスケール練習を取り入れてみてください。
・メジャースケール(ドレミファソラシド)
・マイナースケール(ラシドレミファソラ)
・五度、三度など特定のインターバル跳躍練習
・スタッカート・レガートなど歌い方を変えた練習
また、単に「音階をなぞる」だけでなく、一音一音の位置と高さを意識することが重要です。
慣れてくると、音を聞いただけで次の音の高さが予測できるようになり、曲を初めて歌うときでも音程を外しにくくなっていきます。
楽譜を読む力と相対音感の養成法

音程力を高めるうえで欠かせないのが、楽譜を読む力と、相対音感の育成です。
絶対音感がなくても、相対音感(基準となる音に対してどれだけ高い・低いかを判断する力)があれば、音程のズレを瞬時に把握し、修正することができます。
まず楽譜を読む力を身につけることで、視覚的に音の上下関係が理解できるようになります。
たとえば「この小節では、前の音よりも3度上がる」といった情報が目から得られるため、実際に声に出す前に「どのくらい音を上げるか・下げるか」を予測できます。
具体的なトレーニング方法としては、
・音符の名前と高さを声に出して読む「ソルフェージュ」
・簡単なメロディーの視唱(楽譜だけを見て歌う練習)
・メロディー模写(音を聞いて楽譜に起こすトレーニング)
などがあります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、続けていくうちに音を聞いて音程を捉える力=相対音感が少しずつ育っていきます。
また、音感トレーニングアプリやソルフェージュ教材を活用するのもおすすめです。
近年では、スマホアプリを使って手軽に視唱や聴音の練習ができるようになっており、毎日のスキマ時間でも効率的に音感を磨くことができます。
ピッチ補正とその活用法

現代の音楽制作において、「ピッチ補正」は避けて通れない技術のひとつです。
レコーディングの現場では、どんなに歌が上手い人でも、ほんのわずかにピッチがずれることがあります。
そうした微細なズレを修正し、曲全体の完成度を高めるために活用されているのがピッチ補正ソフトです。
と聞くと、「機械で歌を修正するなんてズルい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ピッチ補正は単なる「ミスのごまかし」ではなく、むしろ音楽表現を支えるための重要なツールとして進化してきたものなのです。
ここでは代表的な補正ソフトである Auto-Tune や Melodyne の機能、そして「補正=悪」とは限らない、ピッチ補正の芸術的側面について丁寧に解説していきます。
Auto-TuneやMelodyneでできること

ピッチ補正ソフトの代表格といえば、Antares社の Auto-Tune と Celemony社の Melodyne。
この2つのソフトは、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。
まずAuto-Tuneは、リアルタイムでのピッチ補正が得意なソフトです。
設定次第では、自然な補正から機械的なロボットボイス(いわゆるケロケロボイス)まで幅広く対応できるため、ポップスやEDMなどでは表現手法としても積極的に使われています。
一方でMelodyneは、録音後の音源を時間軸とピッチの両面から精密に編集できるのが特徴です。
音の長さ、音量、ビブラート、音の立ち上がりなど、細かいニュアンスにまで手を加えることができるため、非常に自然な仕上がりが得られます。
プロのレコーディング現場でも、「違和感のない補正をしたい場合はMelodyne」と言われるほど、その性能は高く評価されています。
これらのソフトを用いれば、たとえピッチが多少不安定だったとしても、後から美しく整えることが可能です。
しかし、ここで注意したいのは、「補正を前提に歌う」のではなく、「本来の歌唱力を高めたうえで補助的に活用する」ことが大切だという点です。
加工とアートとしてのピッチ補正
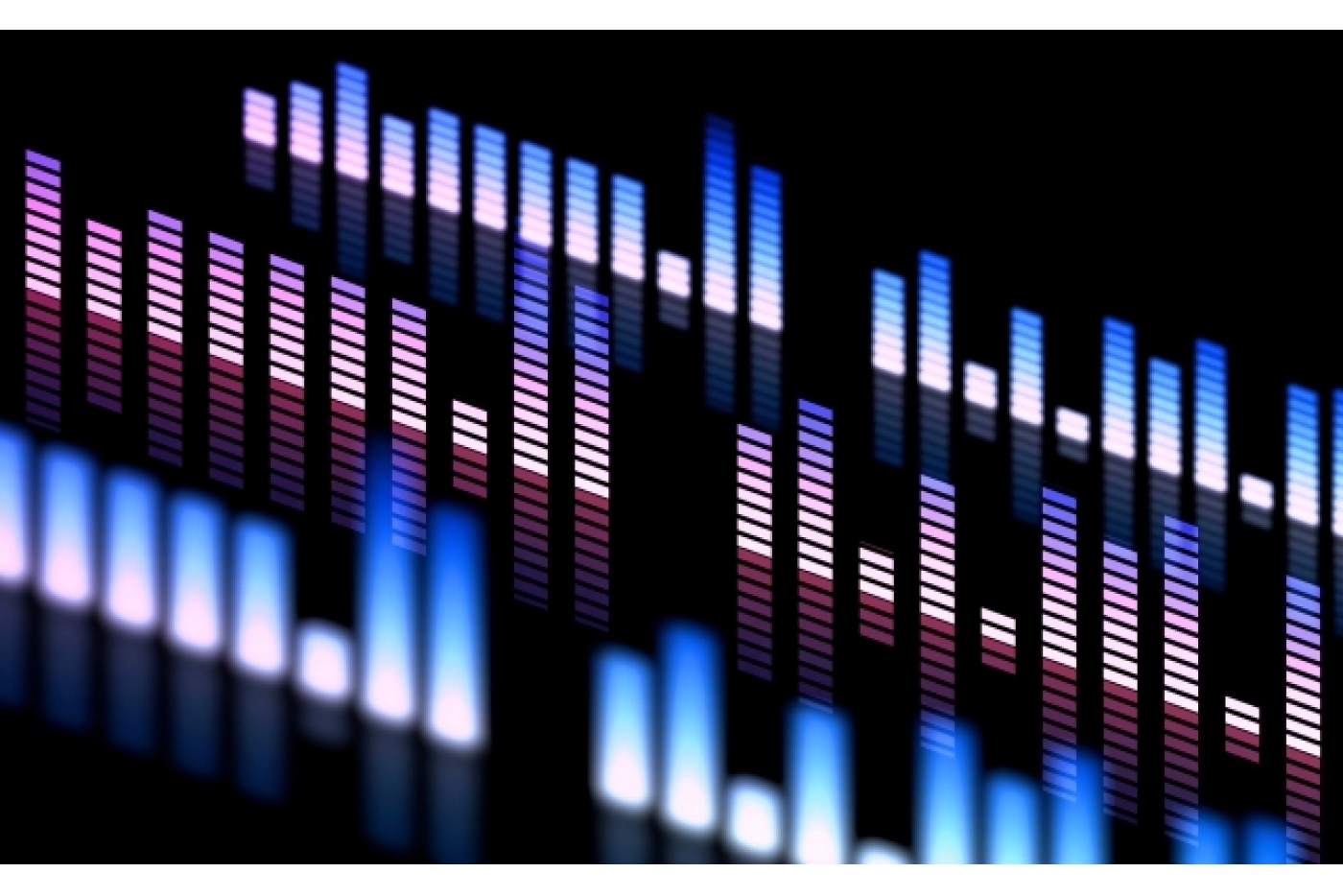
ピッチ補正の目的は、単なる「音の正しさ」にとどまりません。表現としての意図的な加工に活用されることも少なくないのです。
たとえば、T-Painや初期のKanye West、さらにはPerfumeやきゃりーぱみゅぱみゅのように、Auto-Tuneをあえて強くかけた「デジタル感のあるボーカル」は、そのアーティストの個性として多くのファンを魅了しています。
これらは「補正」というより、むしろ音楽的なエフェクト=効果音としての使い方に近いものです。
また、映画音楽やアニメソング、ボカロ曲などの制作現場では、現実離れした声の質感を出すためにピッチ補正が用いられることも多く、加工は表現の一部として受け入れられています。
つまり、ピッチ補正は「間違いを直す道具」であるだけでなく、「音楽的な世界観を構築するツール」にもなり得るのです。
使い方次第で、あなたの歌声はより洗練され、聴く人に強い印象を与えることができるでしょう。
ピッチ・音程の改善を目指すボイトレ活用法

歌を上達させたいと願う方の多くが抱える悩み。
それが「ピッチが不安定」「音程が正確に取れない」という問題です。
練習しているつもりでもなかなか改善されず、「自分には才能がないのかも…」と諦めかけてしまう方も少なくありません。
しかし、実はこのような悩みは正しいアプローチと継続的なトレーニングによって大きく改善することができます。
それでは次に、ピッチや音程の改善に効果的なボイストレーニングの活用法について、ご紹介します。
プロによるフィードバックの重要性

ピッチや音程のズレは、自分では気づきにくいものです。
歌っている最中は、声帯の使い方やブレスコントロール、表現などに意識が向いてしまい、細かい音の高さの違いをリアルタイムで感じ取るのは非常に困難です。
そこで重要になるのが、第三者による客観的なフィードバックです。
特に、経験豊富なボイストレーナーからの指導は、自己流では気づけないクセや改善ポイントを的確に教えてくれます。
たとえば、「サビになると音程が甘くなる」「母音の発音が曖昧でピッチがブレやすい」といった具体的なアドバイスは、プロならではの視点から導き出されるものです。
また、トレーナーはその人の声質や音感に合わせた個別の練習メニューを提案してくれるため、ムダのない効率的なトレーニングが可能になります。
何より、定期的なフィードバックを受けることで、歌唱力の変化を「実感」できるようになるのは大きなモチベーションになります。自分の成長を客観的に確認できる環境があるからこそ、継続的な努力が実を結ぶのです。
まとめ
ここまで、「音程」と「ピッチ」の違いを軸に、それぞれの正しい理解や練習方法、そして改善に向けた具体的なアプローチをご紹介してきました。
ふたつの言葉は似ているようでいて、本質的にはまったく異なる概念であり、それぞれに合わせた練習や意識づけが必要です。
「音程」とは、2つの音の間隔を表すもので、メロディラインやハーモニーに深く関係します。
一方「ピッチ」は、1音の高さの正確さを指し、個々の発声の精度に関わる重要な要素です。
ピッチや音程のズレは、歌唱力に直結するだけでなく、聴く人の印象を大きく左右するポイントでもあります。
だからこそ、スケール練習やチューナーの活用、録音によるセルフチェックなど、日々の練習を積み重ねることが大切です。
さらに、現代ではAuto-TuneやMelodyneなどのピッチ補正ソフトも登場し、技術としての活用が進んでいます。ただし、こうしたツールはあくまで補助的なものであり、まずは自分の「耳」と「発声力」を鍛えることが最優先です。
「もっと上手くなりたい」「自分の声に自信を持ちたい」
その気持ちがあれば、必ず成長できます!
練習するならリフレクトスタジオがおすすめ

音程やピッチを意識した歌の練習をするには、練習環境がとても重要です。
名古屋の音楽スタジオ「リフレクトスタジオ」は、練習にぴったりな環境が整っています!
何といっても、録音がとても簡単にすぐできます。
スマホ1台さえあれば、スタジオに常設しているケーブルに繋ぐだけで簡単に録音ができますので、音程やピッチの確認がすぐにできます!
また、非会員制の音楽スタジオとなっておりますので、いつでも好きなタイミングで気軽に利用することができます。
リフレクトスタジオは名古屋市内に4店舗ありますので、公共交通機関を利用してのアクセスは徒歩圏内、お車の方も安心してご利用いただける駐車場も無料でご用意しております!
ピッチが合っているか一目で確認できる「ROLAND ボーカルトレーナー VT-12-EK」も無料レンタルしていただけます。
また、オンラインレッスンに最適な大画面が常設されているスタジオもあり、ダンスなど動きながら歌う場合には、広さがじゅうぶんにあるダンススタジオも利用でき、無料でワイヤレスマイクをレンタルすることも可能です!
「初めてスタジオを利用するから不安…」という方も、安心してください!
利用前にご見学することももちろんできますし、わからないことや不安なことなどがあれば、事前にご相談していただくことももちろん大丈夫です!
見学のご予約や、実際に利用するご予約、お問い合わせなどはLINEで簡単にすることができます。
↓↓簡単LINE予約、お問い合わせはこちら↓↓

関連するおすすめ記事
オススメのスタジオ
 新栄店
新栄店-
A1スタジオ【新栄店】〜6名くらい
Astタイプは専門家が集音計算を実施し、デッドに吸音を整えつつ、迫力も出るようにほどよく反響音もわざと残した抜群の音周り設計! 3つの転がしモニタとドラム専用のモニタの計4つのスピーカーを常設最適なモニタ...
 新栄店
新栄店-
B2スタジオ【新栄店】〜7名くらい
16帖の広さを確保!最も多くの吸音材を使用した部屋で、極限までデッドな環境に! Bstはスタンドタイプのスピーカーを設置!スッキリしたキレイな音周りを表現! ドラムはTAMA最高グレードSTARCLASSIC採用!!全ての...
 新栄店
新栄店-
C1スタジオ【新栄店】〜10名くらい
22帖の驚異的な広さ!!ビッグバンドでも余裕で演奏できる環境です!! 導入スタジオ唯一!??ドラムセットにSAKAEから最高最上機種CELESTIALを採用!!! 1000w級スピーカー+フットモニタで抜群のモニタリング! ライン録...
 新栄店
新栄店-
A6スタジオ【新栄店】〜6名くらい
Astタイプは専門家が集音計算を実施し、デッドに吸音を整えつつ、迫力も出るようにほどよく反響音もわざと残した抜群の音周り設計! 3つの転がしモニタとドラム専用のモニタの計4つのスピーカーを常設最適なモニタ...