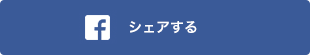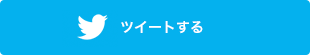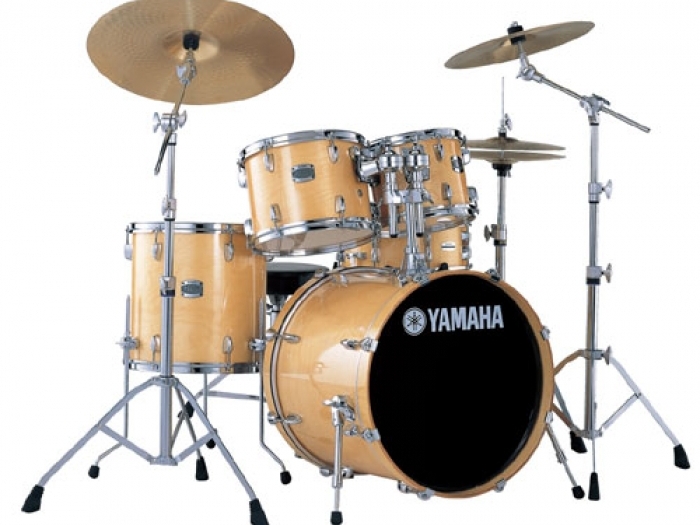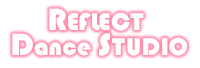1

202507/08
ナレーション録音のコツ!自宅とスタジオの比較と実践テクニック

ナレーションの録音は、YouTube動画、企業プロモーション、eラーニング、オーディオブック、ラジオ番組など、さまざまな音声コンテンツに欠かせない要素です。
以前は専門スタジオでプロが行うものでしたが、近年は自宅でも高品質なナレーションを録音できる環境が整いつつあります。
とはいえ、「どうやって録音するの?」「どんな機材が必要?」「自宅とスタジオでは何が違うの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ナレーション録音に関する基本的な知識から、実際の録音方法、環境の整え方、プロへの依頼方法に至るまで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます!
ナレーション録音の基礎

ナレーション録音に挑戦する際、まず押さえておきたいのが「録音方法の選び方」と「環境づくり」です。
どちらも音質や仕上がりに大きな影響を与えるため、録音前にしっかりと理解しておくことが大切です。
録音方法は大きく分けて「自分の声を使う」「ナレーターソフトを使う」「プロに依頼する」という3つの選択肢があり、目的や予算、求める品質によって最適な方法が異なります。
しかし、録音環境が整っていなければ満足のいく音声は収録できません。
実は部屋の反響や生活音など、意外なところに音質を下げる原因が潜んでいたりするので、録音方法を選択する前に環境を整えていきましょう。
それでば、ナレーション録音のスタートラインとなる基本事項について、ご紹介していきます。
録音方法の選択

ナレーションを録音する方法にはさまざまな手段がありますが、大きく分けると
①自分で録音する
②ソフトで音声を生成する
③ナレーターに依頼する
の3つに分類されます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の用途や目的によって最適な手段が変わってきますので、詳しく説明していきます。
①自分の声を使う方法

最も手軽で柔軟性のある方法が、「自分でナレーションを録音する」スタイルです。
パソコンやスマホとマイクさえあれば、今日からでも始められるこの方法は、YouTuberや個人の音声作品、社内用の資料ナレーションなど、さまざまな用途で活用されています。
自分の声なら、感情の込め方やテンポも自由自在です。
納得いくまで何度でも録り直しができるのも大きなメリットです。
加えて、録音環境やスキルが整えば、プロ並みの仕上がりを目指すことも可能です!
ただし、録音には最低限の機材やソフトの知識が必要であり、滑舌や発声にも気を配る必要があります。
「自分の声に自信がない」「一度聞いてみてほしい」といった方は、無料の録音アプリでを活用して練習してみるのも良いでしょう!
②ナレーターソフトの活用

近年では、AI音声や合成音声を用いたナレーターソフトも注目を集めています。
簡単な原稿を入力するだけで、ナチュラルなナレーション音声を生成できるため、手間をかけずにコンテンツを作りたい方には非常に便利です。
特に、動画内の字幕に合わせて音声を作成するケースや、短時間で大量のナレーションを必要とする場面では重宝されます。
複数の声色から選べるソフトも多く、シーンに応じた演出も可能です。
一方で、抑揚や間の取り方に限界があり、どうしても「機械的な印象」が残ることがあります。
聞き手に感情を伝えたいコンテンツでは、やや物足りなく感じるかもしれません。
無料の試用版があるので、そちらを活用して自分の目的に合うかどうか確認してみるのも良いでしょう!
③プロのナレーターに依頼する方法

「品質を最優先したい」「商用利用で信頼性が求められる」そんな方には、プロのナレーターに依頼する方法が最適です。
経験豊富なナレーターが、原稿の意図をくみ取り、聞き手の心に響く声でナレーションを提供してくれます。
また、プロが利用する録音スタジオは、防音設備や高性能な機材が整っており、ノイズの少ないクリアな音声が収録可能です。
制作会社や音響スタジオを通じて依頼することで、編集やミキシングも含めてトータルでサポートを受けることができる点も安心です。
費用はかかりますが、ブランディングや印象に直結する重要なコンテンツには、価値があるでしょう。
「こんなナレーションを作りたいけど、どう頼んだらいいかわからない」と迷ったら、気軽にスタジオに問い合わせてみるのもおすすめです。
この記事の最後におすすめのレコーディングスタジオをご紹介します!
録音環境の整備

どんなに良いマイクやナレーターを使っても、録音する環境が整っていなければ、クリアな音声は手に入りません。
実は、音声の質を左右するのは、機材以上に「空間」なのです。
それでは、初心者でも実践しやすい録音環境の整備ポイントをご紹介していきます!
反響の少ない部屋の選択
録音時に気をつけたいのが、声が壁や天井に跳ね返って響く「反響音(リバーブ)」です。これが強いと、声がこもったり、聞き取りづらくなってしまいます。
理想は、防音材や吸音パネルが設置された専用の収録ブースですが、自宅でも工夫次第で対応可能です。
たとえば、
・布団に囲まれたクローゼット内
・カーテンやカーペットで囲まれた部屋
・厚手の布や毛布を壁にかける
など、音の跳ね返りを防ぐ工夫をするだけでも大きく改善されます。
家具が多い部屋や本棚がある空間も、音を吸収しやすくおすすめです。
ノイズ源の特定と対策
意外と見落とされがちなのが、日常生活に潜む「ノイズ源」です。
録音中に「ブーン」という音や「カタカタ」といった小さな物音が混ざってしまうと、ナレーションのクオリティは一気に低下します。
よくあるノイズの原因には、
・パソコンや空気清浄機のファン音
・冷蔵庫やエアコンの作動音
・外の車や工事音
・隣人や家族の足音・話し声
などがあります。
録音前に部屋の音を一度無音で録ってみて、ノイズが入っていないか確認するのが効果的です。
また、ノイズ対策としては、
・機器を一時的にオフにする
・窓やドアを密閉する
・録音時間帯を変えてみる(早朝や深夜)
・リフレクションフィルターやポップガードを併用する
といった方法があります。
どうしても避けられない場合は、ノイズ除去ソフトを使って後処理を行うのも手です。
必要な機材と選び方
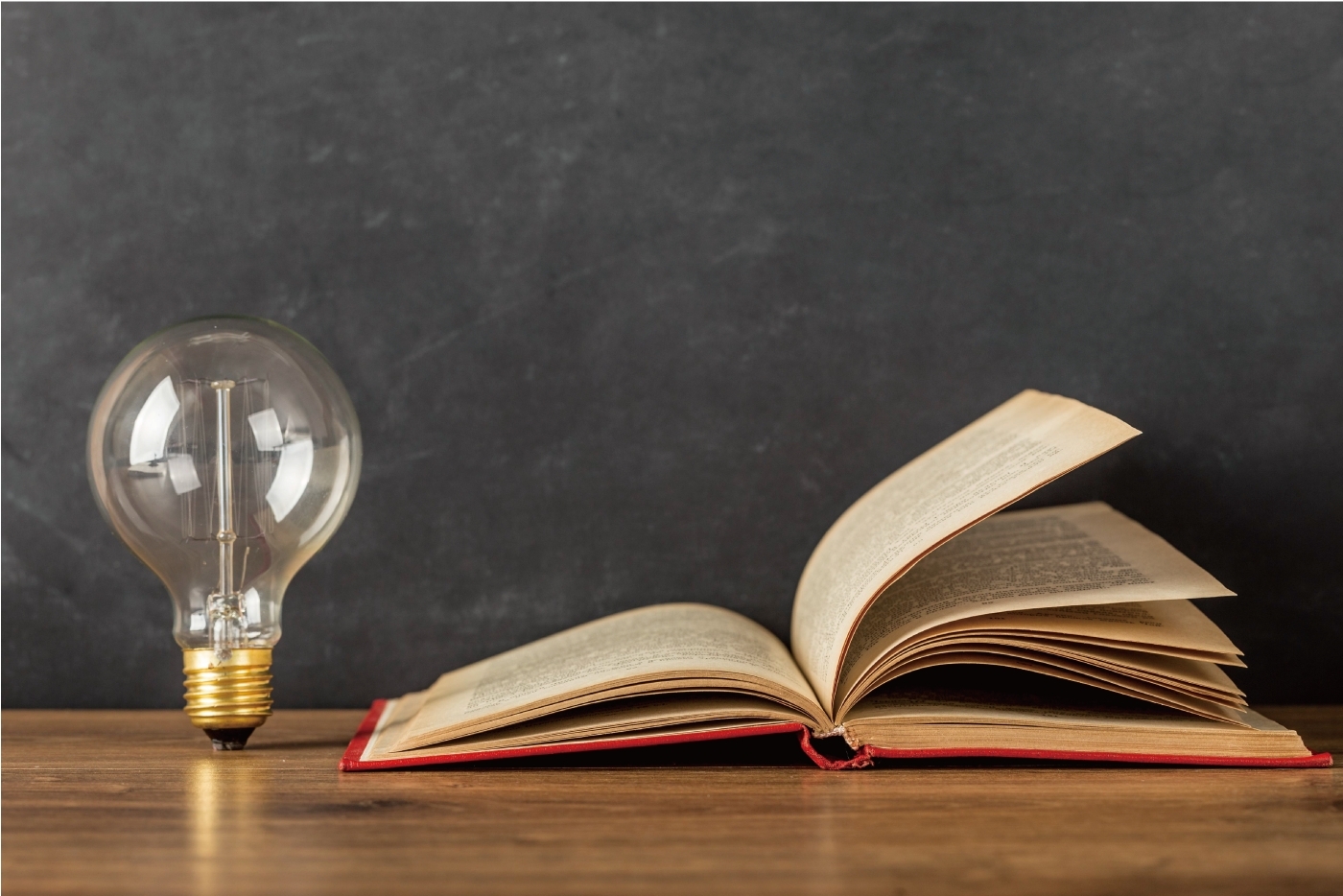
ナレーション録音の音質を大きく左右するのが、使用する「録音機材」です。
どんなに良い声や環境が整っていても、機材の選定が不適切であれば、思うようなクオリティには仕上がりません。
ここでは、ナレーション録音において特に重要な
①マイク
②オーディオインターフェイス
③補助機材
の、3つのカテゴリに分けて、それぞれの役割や選び方、そしておすすめ製品をご紹介していきます。
これから機材を揃える方はもちろん、買い替えやグレードアップを検討している方も、ぜひ参考にしてみてください!
①マイクの選択

ナレーション録音において最も重要な機材が「マイク」です。
自分の声をどのように、どれだけクリアに収音できるかが、マイクの性能にかかっています。
ここでは、用途に応じたマイクの種類と、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。
ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの比較
マイクは大きく分けて「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」に分けられます。どちらもナレーション録音に使用できますが、性能や特徴に違いがあります。
・ダイナミックマイク
ダイナミックマイクは頑丈で取り扱いが簡単、環境ノイズにも強いため、ライブパフォーマンスや騒音のある環境での使用に向いています。
しかし、音の感度が低めで、繊細な声のニュアンスを捉えるのがやや苦手です。
・コンデンサーマイク
一方、コンデンサーマイクは感度が非常に高く、人の声の細かい表現や息づかいまで忠実に再現できます。
録音スタジオでもプロが使用しており、ナレーションやボイスオーバーの収録にはこちらがおすすめです。
ただし、湿度や衝撃に弱く、ファンタム電源(+48V)を必要とするため、扱いには注意が必要です。
USBマイクのメリットとデメリット
最近では、USB接続タイプのマイクも人気です。
パソコンに直接つなぐだけで録音が可能で、オーディオインターフェイスを必要としない手軽さが魅力です。
◇メリット
・セットアップが非常に簡単
・コストパフォーマンスが高い
・録音ソフトと組み合わせるだけですぐに使える
◆デメリット
・音質面ではXLR(キャノン端子)接続のマイクに劣ることがある
・拡張性が乏しく、機材のアップグレードが難しい
・高度な編集やプロ仕様の録音にはやや不向き
初めてナレーション録音に挑戦する方や、予算を抑えて始めたい方にはUSBマイクは非常におすすめです。
将来的により高音質を目指す場合は、XLRタイプ+オーディオインターフェイスへのステップアップを検討してみるのも良いでしょう!
おすすめマイクのラインナップ
それでは、ナレーション録音に適したマイクをいくつかご紹介します。
用途や予算に応じて選んでみてください。
・Audio-Technica AT2020(コンデンサー/XLR)
高音質かつ手ごろな価格で、多くのナレーターや配信者に支持される定番モデルです。
・RØDE NT1-A(コンデンサー/XLR)
非常に低ノイズで、繊細な音の再現に優れたスタジオ定番機。
ナレーションや歌録りにおすすめです。
・Blue Yeti(USB)
多指向性対応で使いやすく、ポッドキャストやナレーション録音に最適なUSBマイクの代表格。
・SHURE SM7B(ダイナミック/XLR)
放送局でも使用される高性能マイク。
やや価格は高めですが、声の深みをしっかりと収録できます。
②オーディオインターフェイス

XLR接続のマイクを使用する際には、「オーディオインターフェイス」が必要です。
これは、アナログの声をパソコンが理解できるデジタル信号に変換する装置で、音質や遅延にも大きく影響します。
選び方のポイント
オーディオインターフェイスを選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう。
・マイク入力端子(XLR)の有無と数
1人で録音するなら1つで十分。複数人で使う場合は2つ以上必要です。
・ファンタム電源の供給が可能か
コンデンサーマイクを使用するにはファンタム電源(+48V)が必要です。
・モニタリング機能
自分の声をリアルタイムで確認できるヘッドホン端子やモニターボリュームは必須です。
・持ち運びやすさ・接続方式(USB-Cなど)
ノートPCと一緒に使うなら、小型軽量タイプやUSB-C対応が便利です。
人気モデルの紹介
以下は、初心者から中級者に人気の高いオーディオインターフェイスの一例です。
・Focusrite Scarlett 2i2
ナレーションやボーカル録音の定番。音質・操作性ともに優れており、初めての1台に最適。
・Steinberg UR22C
安定性と堅牢性があり、DAWとの親和性も高い。クリエイターに人気。
・MOTU M2
高音質と低遅延を両立し、視覚的に見やすいメーターが特徴。中〜上級者にもおすすめです。
③補助機材

音質をさらに高め、よりナレーションらしいプロらしい収録を実現するためには、「補助機材」も大切です。
ここでは特に導入したい2つのアイテムをご紹介します。
ポップガードとリフレクションフィルター
・ポップガード(ポップブロッカー)
「パピプペポ」などの破裂音がマイクに吹き込むことで生じる「ポップノイズ」を抑えるアイテムです。
マイクの前に設置するだけで、声の不快な破裂音を防ぎ、聞き取りやすい音声を実現できます。
・リフレクションフィルター
マイクの背後に設置することで、不要な反響音や周囲のノイズを遮断するアイテムです。
特に自宅収録では効果が大きく、スタジオのような音質に近づけることが可能です。
どちらも手頃な価格で購入できるため、これからナレーションに本格的に取り組みたい方には強くおすすめします。
録音テクニックとコツ

ナレーションのクオリティを左右するのは、機材や環境だけではありません。
実際に録音する際の「テクニック」や「準備の仕方」も、音声の印象を大きく左右します。
たとえば、原稿の読み方ひとつで聴きやすさが変わり、マイクの距離や角度によって音質も大きく変化します。
また、録音後の編集作業でノイズを除去したり、音量を均一に整えることによって、プロのような仕上がりを目指すことも可能です。
それでは、ナレーション録音をより高品質に仕上げるための「実践的なテクニック」を、原稿の扱いから編集作業まで順を追って解説していきます。
原稿の準備と扱い方

効果的な原稿作成法
ナレーション録音では、原稿が「声の設計図」とも言えるほど重要です。
内容のわかりやすさや言葉のリズム、読みやすさを意識して作成することで、ナレーターが自然なイントネーションで読み上げられ、聞き手にも伝わりやすくなります。
以下のポイントを押さえることで、原稿の質をぐっと高めることができます。
・短い文節で構成する:長い一文は息継ぎが難しく、聞き手も理解しにくくなります。
・漢字とひらがなのバランスをとる:難読漢字や専門用語にはルビをふるなど、読みやすさを意識。
・間(ま)を入れたい場所に印をつける:原稿にスラッシュ「/」や改行を入れることで、読み手がテンポを取りやすくなります。
録音前に原稿を声に出して読み上げ、リズムや言い回しに違和感がないか確認する「読み合わせ」も効果的です。
ページめくりの音を防ぐテクニック
紙の原稿を使用する場合、録音中に「ページをめくる音」が入ってしまうことがあります。
特に静かなナレーションでは、この音が目立ちやすくなり、音声編集でカットするのが難しいこともあります。
以下の工夫で、ノイズを最小限に抑えることができます。
・原稿をA4サイズで片面印刷し、見開きで使用する
・ファイルやバインダーにセットし、静かにページを送る練習をする
・タブレットやスマートフォンなど電子デバイスを使う(画面タップの方が静かです)
また、録音中にページをめくるタイミングをあらかじめ決めておき、必要があれば「一時停止→再開」で編集に備えるのも効果的です。
音質向上のテクニック

マイク位置の最適化
マイクの位置は、音質に直結する重要な要素です。
「良いマイクを使っているのに、なんとなく声がこもる」「息が強く当たりすぎる」などのトラブルは、マイクの距離や角度に原因があることが少なくありません。
基本的なマイク配置のコツは以下の通りです。
・マイクとの距離は約15〜20cm程度:近すぎるとポップノイズが入り、遠すぎると声が弱くなります。
・真正面ではなく、少し斜めから話す:息が直接マイクに当たるのを防げます。
・ポップガードを使って息の吹かれをコントロールする
録音前には実際にテスト録音をして、声のクリアさやバランスを確認してから本番に臨むことが大切です。
録音レベルの調整
ナレーション録音では、録音時の音量(レベル)を適切に設定することが非常に重要です。音量が小さすぎるとノイズが目立ちやすく、大きすぎると音割れの原因になります。
録音レベル調整のポイントは以下の通りです。
・ピークが−6dBから−3dB程度に収まるように設定する
・大きな声と小さな声のバランスを想定し、適度に余裕を持つ
・オーディオインターフェイスや録音ソフトのメーターを常に確認する
録音レベルは一度決めたら途中で変更せず、一定のボリュームで話すよう意識しましょう!急に声のトーンが変わると、聴き手にとって不快に感じられることがあります。
後処理と編集
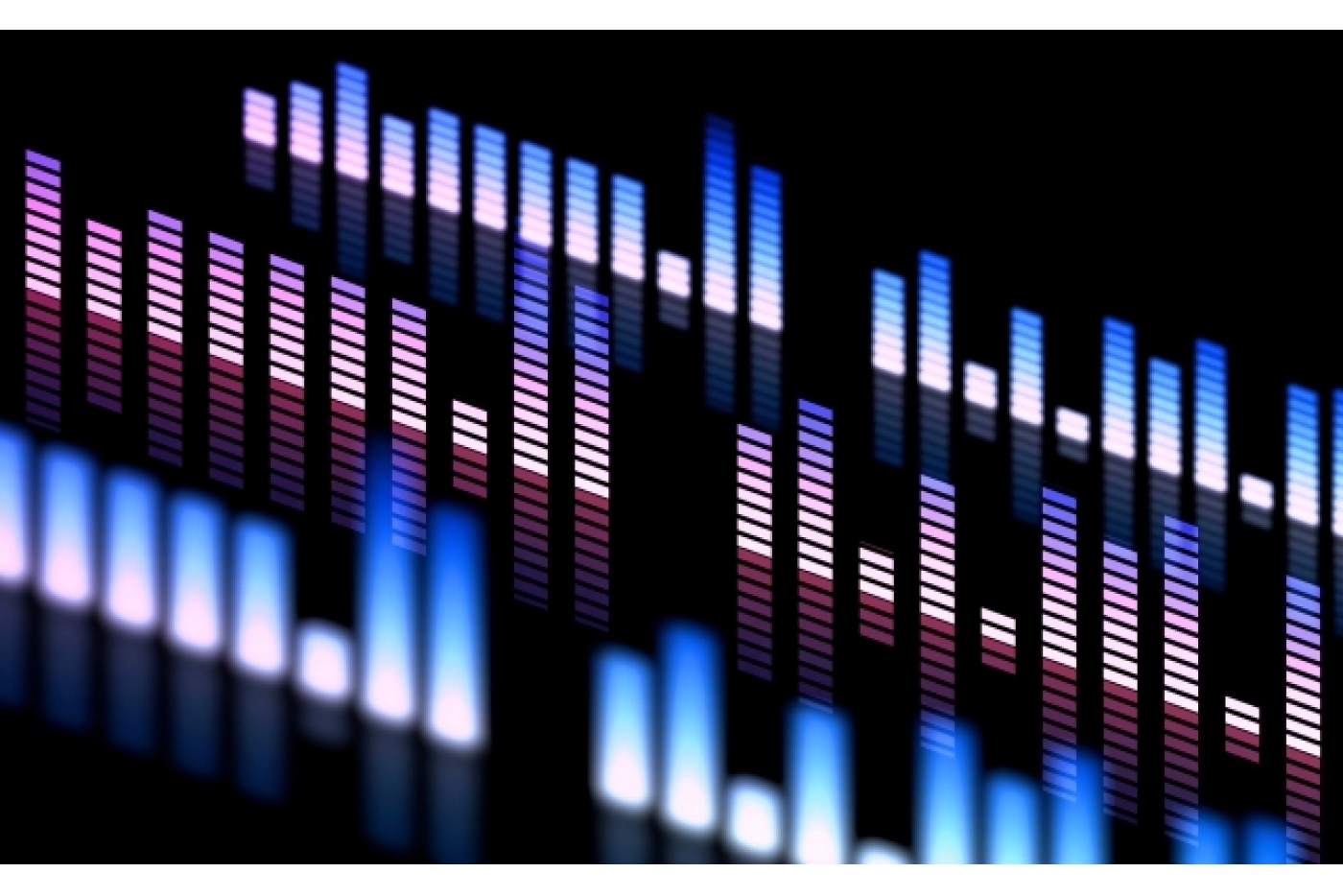
ノイズ除去ソフトの活用
どんなに静かな環境で録音しても、微細なノイズは避けられません。
空調の音、パソコンのファン、わずかな環境音などが録音に入ることがあります。
そのような場合には、ノイズ除去ソフト(プラグイン)を活用することで、音質を大きく改善することが可能です。
おすすめのノイズ除去ツールには以下があります。
・iZotope RX(アイゾトープ アールエックス):プロも使用する高機能な音声編集ソフト。特にノイズ除去機能が非常に優秀。
・Audacity(オーダシティ):無料で使える定番編集ソフト。基本的なノイズリダクション機能が搭載されています。
ノイズ除去は「やりすぎると音声が不自然になる」こともあるため、適度な調整が大切です。
音声編集の基本テクニック
録音が完了したら、音声をより聞きやすく、プロらしく仕上げるために編集作業を行います。
以下のような処理を行うことで、完成度を大きく高めることができます。
・無音部分の調整(カット・フェード)
・音量の均一化(ノーマライズやコンプレッサー)
・不要な呼吸音やリップノイズの削除
・BGMや効果音の挿入(必要に応じて)
編集ソフトはAdobe AuditionやReaper、Audacityなど、用途やスキルに応じて選ぶとよいでしょう!
初めての方でもしっかり編集すれば、十分に高品質なナレーションを仕上げることができます。
自宅録音とスタジオ録音の比較

ナレーションを録音する際、「自宅で録るべきか、それともスタジオに依頼すべきか」で迷われる方は多いのではないでしょうか。どちらにもそれぞれの魅力と特徴があり、目的や予算、納期によって最適な選択は異なります。
それでは次に、自宅録音とスタジオ録音、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、どんな方にどの方法が向いているのかを解説していきます。
ナレーション制作を成功させるためには、技術や機材以上に「適切な方法を選ぶこと」が非常に大切です。
自宅録音のメリットとデメリット

自宅での録音は、最近ではテレワークの普及や低価格の音響機材の登場によって、ぐっと身近な選択肢となっています。
以下に、自宅録音の主なメリットとデメリットを挙げてみました。
◇メリット
・コストを抑えられる
スタジオのレンタル費やナレーターの依頼料が不要なため、予算を節約したい方には非常に魅力的です。
・いつでも録音できる
時間の都合に合わせて好きなタイミングで録音できるため、柔軟にスケジュールが組めます。
・リテイクがしやすい
録り直しや細かい修正が必要になったときも、自分で対応できる点は大きな利点です。
◆デメリット
・音質に限界がある
プロ仕様の防音・吸音環境がないと、雑音や反響がどうしても入りやすく、仕上がりに差が出ます。
・ナレーション技術や編集知識が必要
自然な話し方や正確な録音レベルの調整、ノイズ除去など、ある程度の経験やスキルが求められます。
・聞き手に不信感を与える可能性
特に企業動画や広告など、信頼性が求められる場面では、録音クオリティの差が印象に直結することもあります。
このように、自宅録音は手軽でコストパフォーマンスに優れていますが、品質面での妥協が発生しやすい点には注意が必要です。
「まずは自分で試してみたい」「趣味や小規模プロジェクトで使いたい」という方にはおすすめですが、商用や公式な用途で使う場合には慎重な判断が求められます。
スタジオ録音の利点

スタジオでの録音は、プロフェッショナルな機材と環境、そして人材が揃っているため、仕上がりにおいて非常に高いレベルが期待できます。
以下にて、その主な利点をご紹介していきます。
高品質な音声
スタジオ録音の最大の魅力は、なんといっても音質の高さです。
・音響設計された空間で録音されるため、反響やノイズのないクリアな音声が得られる
・プロ用マイクやオーディオインターフェイス、ミキサーなど、最適にチューニングされた機材を使用
・音声エンジニアが常駐している場合、録音レベルや音質の調整をその場で対応してもらえる
特に、企業プロモーション動画、テレビCM、教材音声、オーディオブックなど、聞き手に「信頼感」や「印象の良さ」を伝えることが求められる用途には、スタジオ録音が強く推奨されます。
多様なキャスティングオプション
スタジオを利用するもうひとつの大きな利点は、プロのナレーターを選んで依頼できることです。
・男女、年齢、話し方のスタイル、声質など、多彩なナレーターから選べる
・シナリオや用途に応じて最適な声をキャスティングできる
・演技力や滑舌、発声の安定性など、素人では出せないクオリティが保証される
特に広告や企業VP、ナレーション付きのeラーニングコンテンツなど、「ブランドイメージを声で伝えたい」場面では、プロのナレーターによるスタジオ録音が圧倒的に有利です。
スタジオ録音なら、リフレクトレコーディングがおすすめ

自宅録音とスタジオ録音、それぞれにメリットと課題があります。
「費用は抑えたいけど、なるべく良い音で録りたい」「プロの声を使いたいけど、どこに依頼すればいいかわからない」とお悩みの方も多いことでしょう。
そんなときは、プロに相談してみてはいかがでしょうか。
とても心強い味方になります。
私たちリフレクトレコーディングは、初めての方でも安心してご利用いただけるよう、目的に合った録音スタイルの提案や、ご予算に応じた機材の選定、スタジオ録音のご案内などを丁寧にサポートしております。
ナレーション録音は、映像や音声コンテンツの「顔」とも言える重要な作業です。
聞き手に伝わる声の質や表現力が、そのままコンテンツ全体の印象を左右します。
そのため、録音の基礎を理解し、最適な方法と機材を選ぶことは非常に大切です。
今回ご紹介した通り、ナレーション録音には「自分の声を使う方法」「ナレーターソフトの活用」「プロのナレーターに依頼する方法」など様々な選択肢があります。
それぞれのメリットやデメリット、そして録音環境の整備や機材選びのポイントをしっかり押さえることで、より満足度の高い仕上がりが期待できます。
また、録音テクニックや後処理の工夫を加えることで、音質や聴きやすさは格段にアップします。
特にマイクの位置調整やノイズ除去は、初心者の方でも取り組みやすく効果的なポイントです。
ナレーション録音は決して難しいものではありません。
正しい知識と準備があれば、どなたでも質の良い音声を作り出せます。
あなたの声で、素敵なコンテンツを作り上げるお手伝いができることを心より楽しみにしています。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください!
↓↓お問い合わせやご予約はLINEから簡単にしていただけます↓↓
↓↓簡単LINE予約、お問い合わせはこちら↓↓

関連するおすすめ記事
オススメのスタジオ
 今池店
今池店-
A1スタジオ【今池店】〜6名くらい
Astタイプは14帖~15帖という余裕の広さを確保しながら他では考えられないリーズナブルな価格!専門家が計算した反響調整により、迫力のある音を残しつつ、全ての音がはっきり聞こえるようにつくられています。一...
 今池店
今池店-
A3スタジオ【今池店】〜6名くらい
Astタイプは14帖~15帖という余裕の広さを確保しながら他では考えられないリーズナブルな価格!専門家が計算した反響調整により、迫力のある音を残しつつ、全ての音がはっきり聞こえるようにつくられています。一...
 新栄店
新栄店-
A1スタジオ【新栄店】〜6名くらい
Astタイプは専門家が集音計算を実施し、デッドに吸音を整えつつ、迫力も出るようにほどよく反響音もわざと残した抜群の音周り設計! 3つの転がしモニタとドラム専用のモニタの計4つのスピーカーを常設最適なモニタ...
 新栄店
新栄店-
C2スタジオ【新栄店】〜10名くらい
22帖の驚異的な広さ!!ビッグバンドでも余裕で演奏できる環境です!! 導入スタジオ唯一!??ドラムセットにSAKAEから最高最上機種CELESTIALを採用!!! 1000w級スピーカー+フットモニタで抜群のモニタリング! ライン録...